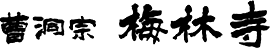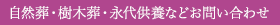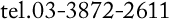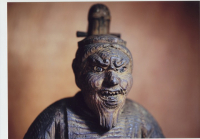阿部将翁の墓 史跡


阿部友之進照任は、江戸中期、徳川吉宗治世期に活躍した本草学者で、その墓は都の旧跡に指定されている(昭和3年指定)。
友之進、名を照任、また輝任、字を伯重、号を将翁(しょうおう)また将翁軒と言い、友之進は通称である。
奥州盛岡出身。東条琴台著『先哲叢談続編』第四巻によると慶応3年(1650)の生まれとされているが、没年の宝暦3年(1753)から逆算すると、104歳で没したことになり、生年に疑問が持たれている。
近年、照任の著になる『金の書』などにより、生年は寛文7年(1667)前後という見解も出された。
照任は、享保12年(1727)に奥州盛岡に、翌年甲斐(現、山梨県)に赴き採薬を果たしている。
同年神田紺屋町(現、千代田区)に薬草植場を貸与され、また同14年、奥羽、蝦夷へ採薬に出掛けたことは幕府の史料で判明しているが、未だ不明な点が多い。
照任の曾孫喜任は字を享、享父、通称・号を曾祖父と同じ友之進、将翁と名乗るが、櫟斎の号を使用することが多い。他に巴菽園、庵の号がある。
本草学を曽占春、岩崎灌園に学び、漢学を登場琴台に学んだ。
文久元年(1861)幕府が派遣した咸臨丸に乗船し小笠原の調査を行うなど実地調査の傍ら、曾祖父照任の事蹟を顕彰することに勤めた。
文化2年(1805)生、明治3年没。